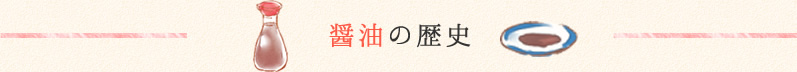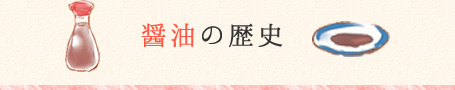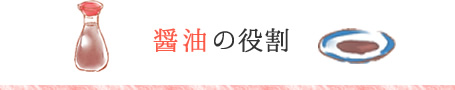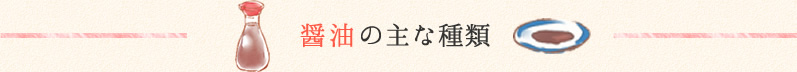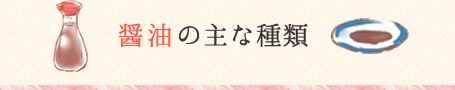「ソイソース(豆のソース)」として、今や世界に進出している醤油。最近では、フランスの三ツ星レストランでも料理の隠し味に醤油を使っている例が少なくないといいます。また、ロシアやアフリカなど、「そんなところでも?!」というほど世界の食卓への浸透度も驚くほど。日本独自の調味料ながら、醤油は世界が歓迎する調味料として、その評価が高まっています。まさに日本の誇りの味ともいえるわけですが、現在、私たちが知っている「醤油」との付き合いは意外に新しく、始まりは鎌倉時代のことです。
ただ、「醤(ひしお)」と呼ばれる、醤油の原形に当たるものの登場はもっと古く、日本書記や万葉集には、その存在が記されています。この先祖をさらにたどると、行き着くのは東南アジア。現在でも東南アジアには魚を使った「魚醤(ぎょしょう)」が用いられていますが、日本の醤油の原形は、どうやらこの魚醤であると考えられています。 それが年月とともに、当時から食の宝庫であった古代中国に伝播され、肉醤や蝦醤、麦醤などとバリエーションが広がった後、日本列島に伝わったのではないかとされています。
本来は多彩なかたちで日本に伝わった醤ですが、その後、肉を使った「醤(ひしお)」は、次第に暮らしの中から消えていきます。その大きな理由は、仏教の不殺生の教えによって肉を食べることを禁じられたことにあります。肉自体を食べてはいけないのですから、当然、獣の肉を使う醤も作られなくなっていったというわけです。 一方、魚やエビなどを使った醤はというと、こちらは禁止されたわけではなかったのですが、大豆などの植物を使った醤のほうがどうやら日本人の味覚には合っていたらしく、それに押しやられるように食卓から消えていくこととなりました。もっとも、この魚を使った醤は完全に消え去ったわけではありません。一部の地域には、その製法を少しずつ変えながらも、土地の味として細々と生き残りました。秋田県の「しょっつる」や石川県の「いしお」、香川県や千葉県の「いかなごしょうゆ」などがその例です。

時代は下って、時は鎌倉時代、覚信(かくしん)という禅宗のお坊さんが経山時味噌という美味しい味噌の製造方法を留学先の中国から持ち帰ります。そして、紀州・湯浅の地にこの経山寺味噌の製造に適した天然水を見つけました。そこで、よりおいしい味噌作りの研究を重ねていたある日、味噌製造に使っていた樽の底にたまった黒い液に目を止めます。何気なくなめてみたところ…これがなんとも風味豊か。当時すでに生まれていた漬物の先祖の漬け菜などと合わせるにも塩加減が良く、またご飯とも好相性と、本来目指していた経山寺味噌よりもおいしい調味料となっていました。これが「醤油」誕生の瞬間です。 といっても、実はこの醤油は今日でいう「たまり(しょうゆ)」。
それでも、世界に誇る洗練された調味料「醤油」への大きな第一歩であったことは間違いないでしょう。 なお、さまざまな記録から、「しょうゆ」の呼称が生まれたとされているのは室町時代。この室町幕府の時代はそれまでの歴史に比べ、文化の花が華やかに咲いた時代。今日に直結する名前が生まれたというのもうなずける話ですね。
西暦でいえば1500年台の後半から1600年台前半、世は戦国時代から江戸幕府成立までの慌ただしい時代。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康など武将の名前ばかりがクローズアップされてしまいます。しかし、武将たちの覇権争いの陰で商人をはじめとする庶民の生活にもさまざまな変化が起こっていました。これは、信長・秀吉・家康がともに国内交易(商売)を奨励したことが理由ですが、その中で、醤油もまた大きな転換期を迎えていました。それは、醤油生産の産業化です。
それまでは各家庭で自家製というのが醤油入手の主流。自家製でなくても、近在で醤油作りの上手な家庭や、精進料理などを作る都合上、調味料製造も家庭よりは多く作っていたお寺などから分けてもらっていました。今日のようにお店で買うというものではなかったのです。 ところが1561年、千葉県の飯田市郎兵衛という人が甲斐の大名・武田氏に納めるために工業といえる規模で醤油製造をスタート。これを契機にしたように工業規模といえる醤油製造が日本各地で始まります。そして、1588年には、醤油作りの祖・覚心の流れを汲んだ生産地・湯浅から初めて「商品」としての醤油が大阪の商人・小松屋伊兵衛のもとに送られていくこととなりました。
醤油の入手・流通態勢に大きな変化があったのが戦国時代なら、味の大きな変化が生まれたのは江戸時代。徳川幕府治世の時代を迎え、日本の新しい中心地となった江戸では人口が爆発的に増加。人が集まれば文化が栄えるのは道理です。当然、料理ひとつとっても、大名の参勤交代をはじめ、全国各地から集まってくる人たちの口から各地の味や産物、料理法などが伝えられるのは当然の成り行き。それが江戸という大きな町の中でさまざまに変化、進展していきます。その中で醤油もまた、江戸の人たちの口に合うように改良が加えられていきました。
しかも、江戸の商人たちが消費するのですから、製造も流通も商売として成立する要素は充分。かくして江戸時代中期、現在私たちが知っている「醤油」が誕生、以後、この江戸発の新しい醤油が一番オーソドックスな醤油として日本の食卓を席巻していくことになったのです。なお、21世紀の昨今では、卵かけご飯専用の醤油、焼肉に合う醤油などユニークで個性的な醤油が多彩に産まれていますが…これもまた、醤油の変革期と言えるかもしれませんね。
関東ではキッコーマン、ヤマサ、ヒゲタ、関西ではヒガシマル、マルキン。これは日本における5大醤油メーカー。5社のうち、キッコーマン、ヤマサ、ヒゲタは、醤油の製造体制に改革を産んだ地・千葉県が発祥。また、西の雄のうち、ヒガシマルは、千葉県同様に早くから醤油製造が行われていた兵庫県が発祥です。ところが、唯一、マルキンだけは後発の西暦1800年台の醤油製造開始。しかも、その故郷は瀬戸内海の小豆島です。 時間的後発、しかも田舎の地。その条件下に生まれた醤油製造会社が5大メーカーに名を連ねているというのも面白い話ですが、これには理由があります。もちろん、企業努力などもあったでしょうが、どうやら一番大きな理由は商品種類。実はマルキン醤油は濃口醤油を最初に商業ベースに乗せた会社。それまでは、醤油といえば「淡口」か、古くからの製法の「たまり」。そこへ登場した濃口醤油は庶民の口にも合い、たちまち食卓に定位置を占めていきました。先発との違いを武器に地位を確立したマルキン醤油。現代でなくても、「商品は個性!」を語るエピソードですね。

日本に醤油が発達した理由は食生活にあります。海に囲まれた日本は魚の宝庫。しかも、仏教の影響で獣の肉を食べることが敬遠されてましたから、魚は重要なタンパク源です。とはいえ、魚には特有の生臭さがあり、とりわけ刺身で食べるとそれが顕著です。もちろん、そんなことは気にならないという方も少なくないでしょうが、たとえ日本人であっても「生ものの生臭さが苦手」という人は意外に少なくありません。そこで醤油。実は醤油は魚の生臭さを消す働きをします。さらに刺身で食べる際には、ワサビがそれを助けます。生臭さが気にならないという人は、一度試しにワサビも醤油も無しに刺身を食べてみてください。醤油の大きな役割を、身をもって知ることになるかもしれませんよ。
もちろん、醤油が力を発揮するのは、刺身に対してだけではありません。他に重要な要素として "旨味"を生み出すという役目があります。よく耳にする「旨味」という言葉ですが、5大味覚の『塩味・辛味・甘味・酸味・苦味』の中に「旨味」は含まれておりません。ところが「旨味」という感覚は確かにあり、しかもそれは、面白いことに日本人だけが感じることのできる味と言われています。 言い換えれば醤油は、「旨味」を知る日本人だからこそ生み出せた調味料とも言えます。今や、世界にも認められている醤油。どうやらこの「旨味」がわかる人は日本だけでなく世界にも存在するようです。それでも、醤油という調味料を完成させ得たということを考えれば、旨味への敏感さは日本人がひときわ優れていたということかもしれませんね。
味だけでなく、香りや見た目も醤油の魅力の一つです。香りはともかく見た目…?なんだか見た目の美しさとは縁遠いような気もしますが、醤油は加熱されることで、私たちの食欲をそそる香りを身につけます。お餅に代表されるように、醤油の漬け焼きや照り焼きはその香りを嗅ぐだけでおなかがグーとなりそうです。 でも見た目は…と、ここで思い出してください。テラテラと光ったお餅の表面、あるいは照り焼きの魚の表面(たとえばブリの照り焼き等)を。あの照りがさらに食欲をそそりませんか。そうなんです。あの美しい"照り"を身につけるのも醤油独特の性質。醤油は、見た目も侮れない調味料というわけです。 ちなみに、質の良い醤油ほど照りも美しいもの。また醤油単体で見た場合でも、新鮮で良質な醤油は茶色といえどもきれいな透明。無色透明のガラス容器に入れ、光に透かしてみればそれがわかります。
その製法上、発酵食品の分類にも入る醤油には適度な塩分やアルコール、有機酸などが含まれています。塩にはもともと殺菌力があるうえ、アルコールや有機酸も働くため、醤油は食材の殺菌にも役立つ調味料として仕上がっています。白いご飯のお伴として根強い人気の佃煮や醤油漬けなどはこれをうまく活かして作られた食品。この殺菌作用も醤油の大きな役割の一つです。どうです、この辺で、醤油への見方がちょっと変わってきませんか。 しかし、まだまだ。さらに醤油の辛味は、甘味を引きたてたり、塩味などと調和して全体的な辛味を抑えたりという特性まで持っています。たとえば、そのままでも充分に辛い塩鮭にうっかり醤油をかけたら、あら、不思議、塩味がマイルドになったような…という経験はありませんか。実はこれは、醤油がその独特の性質を発揮してくれた結果です。 見た目の地味さに反して並ぶ醤油の役割に、うれしい特性…こんな万能調味料を生み出した日本。なんと奥深い国と、ちょっと胸を張ってみたくなりませんか。
卵かけ用の醤油をはじめ、最近多彩になる一方の醤油のバリエーション。個別の商品名として数えていけば、その数は数千に昇るのではないかと言われています。もちろん、これをすべて知っておくというのは、いかなる醤油の本家・日本人でも(専門家でもなければ)無理な話。しかし、どこのお店にもあるレベルの基本的な醤油の種類については知っておいてもよいでしょう。そこで、それらをご紹介。
一番オーソドックスな醤油。シェアも高く、日本で生産される醤油の約8割がこの濃口醤油です。焼き魚や漬物、その他のお惣菜などに使う卓上醤油としてだけでなく、煮物、焼き物、炒め物と大活躍。言い換えれば、この濃口醤油については、どこへ行っても不自由しないということ。生産量が多いということを考えれば、海外に行っても、さまざまな土地で出会えるでしょう。まさに故郷・日本の味と言えます。
「淡口」という名前のために勘違いされやすいのですが、薄味の醤油というわけではありません。むしろ、塩分は濃い口より高め。というのも、醤油はその製造工程において醸造期間を長くすれば色が濃くなります。淡口醤油は、塩を多く入れることで醸造期間を短縮した醤油。つまり、「淡」は「淡色」の「淡」なのです。色が薄いので、たとえば煮物に使えば、濃口にくらべて淡い色合いの上品な姿に仕上がります。京都をはじめ、見た目を淡い色に仕上げることを良しとするお料理づくりの際には重宝される醤油です。
JASの分類では、「再仕込みしょうゆ」。また、生しょうゆの名前で売られていることもよくあります。一般の醤油は製造工程で加熱処理されるのが普通ですが、生揚げ醤油は加熱処理が施されずに仕上げられます。しかも、加熱せずにしっかり発酵させるために、加熱される以前の醤油が混ぜ合わされます。つまり、加熱されないので「生揚げ」。その分、香りや風味が高く仕上がります。お店の醤油コーナーで少しお高めの値段がついているのはこのため。なお、刺身醤油も実は、この生揚げ醤油の分類に入ります。
生産量は醤油全体の1%程度ながら、一部地域では人気根強い白しょうゆ。他の醤油が大豆を主な原料としているのに対し、白醤油は小麦を主原料に作られます。醤油なら主役…のはずの大豆がこと白醤油に関してはサブの役割。また、ほかの醤油に比べて糖度が高いのが特徴。それもあって、煮物の隠し味などに重宝されます。
刺身醤油と混同されることが多いのがこの「たまり」。しかし、生揚(きあげ)醤油のコーナーでもご紹介している通り、たまりはあくまで「たまり」。特長は、他の醤油が大豆と麦を使うのに対し、たまり醸造に使われるのは大豆だけ。しかも、昔ながらの手間のかかる製法で作られます。火を通すと赤みを増すため、家庭用としてよりは、醤油味のせんべいのようなお菓子の味付けによく使われています。
人々の健康志向を受けてうまれた、醤油の中では新顔。基本的には濃口醤油の分類に入る商品が多いようです。JAS規定でも単独の種類には分類されていません。ただ、最近の風潮を受け、その商品バリエーションは広がっています。
どうやら世のグルメ志向を受けて産まれた醤油。普通の醤油は材料の大豆を、油を絞り採ってから使いますが、この醤油は名前の通りに油を搾らない丸のままの大豆を材料に醸造します。だから「丸大豆」。絞られなかった大豆の油分が独特のまろやかさや風味を生み出してくれることから人気が高まりました。